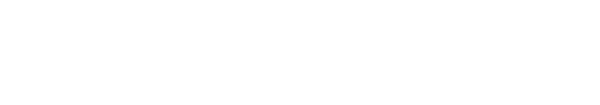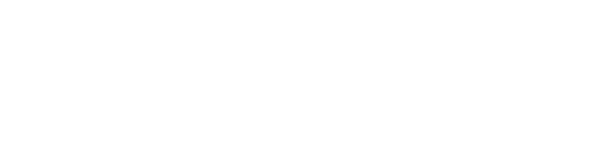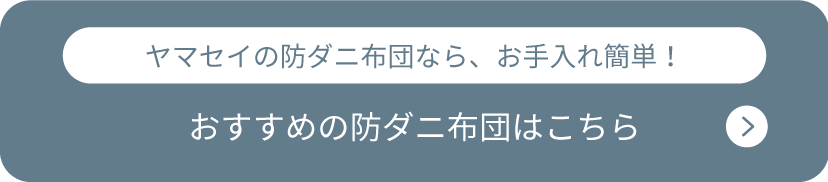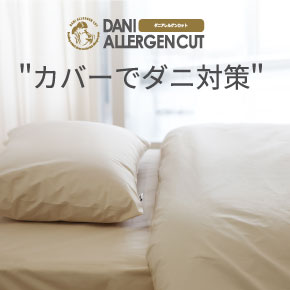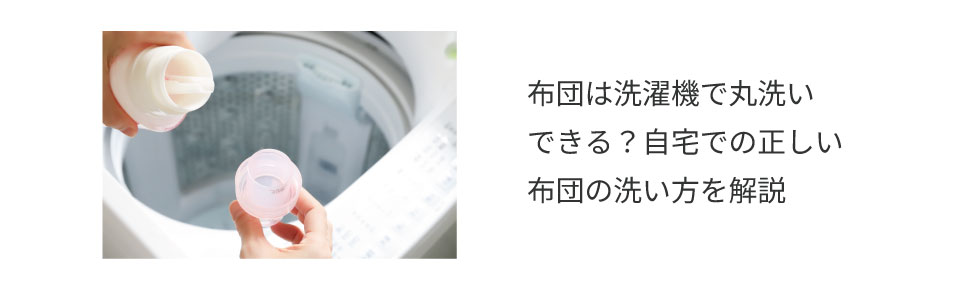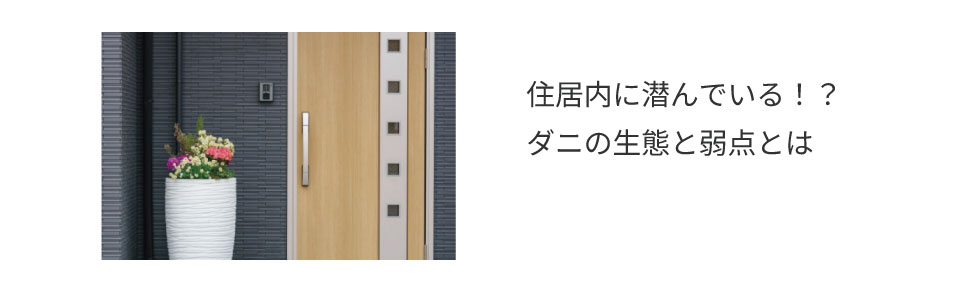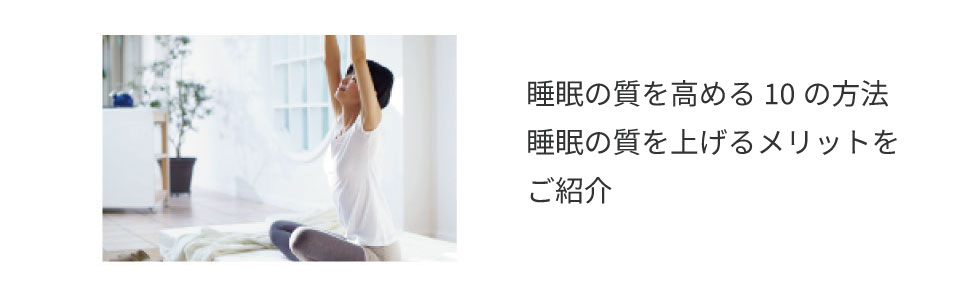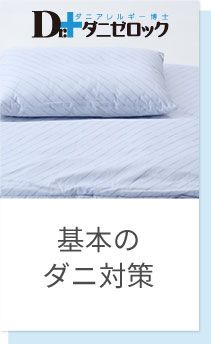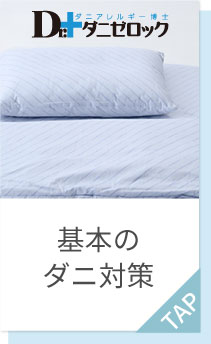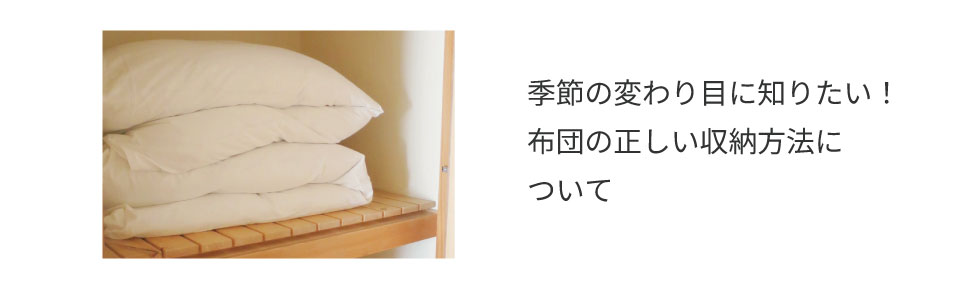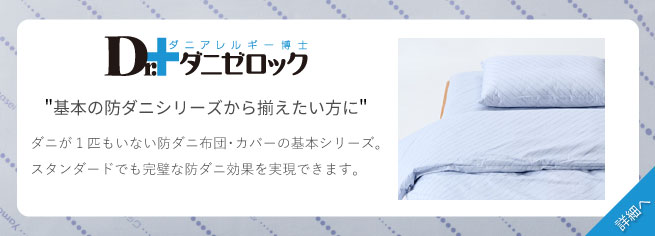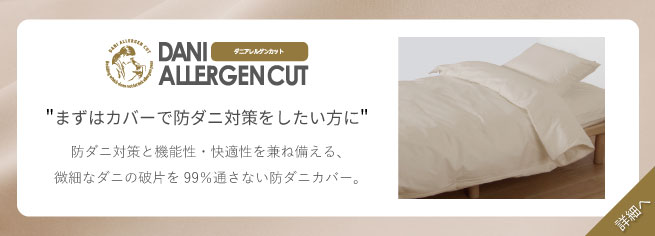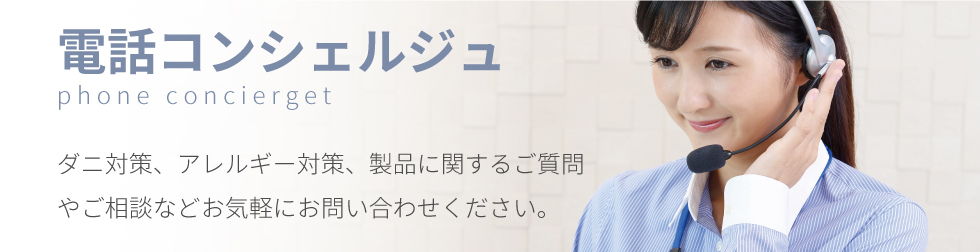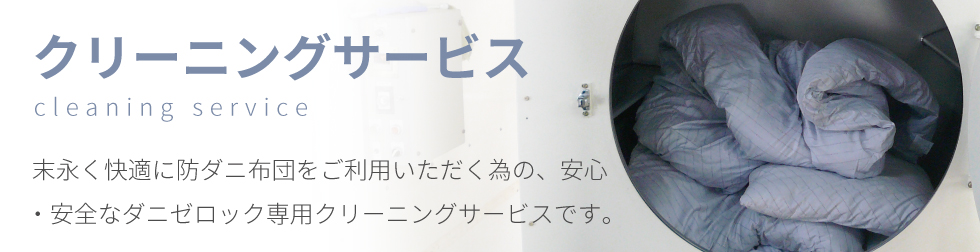究極の布団の干しガイド!ダニを対策し、健康的な眠りを手に入れる
1.究極の布団の干し方ガイド!ダニを撃退し、健康的な眠りを手に入れる
お日様に当たって、ふっくらした布団に寝転がると、心地よい気分で思わず眠ってしまいそうに…。
いつでもそんな快適な布団で眠りたいですよね。寝心地のよいふかふかの布団を保つには、どうすれば良いのか?その答えは、「定期的に布団を干すこと」なのです。
しかし、日常生活が忙しく、なかなか布団を干せない。布団を干そうと思ったら、連日天候が悪い。そもそも干し方が分からない…等、さまざまな理由で布団干しに取り組めない方も多いのではないでしょうか?
そんなお悩みを解決すべく、布団を干す理由と効果をはじめ、布団の干し方・布団を干すのにベストな天候や時間帯等を、ダニ対策についてを交えながら解説します。
2.布団を干す理由と効果について
まずはじめに、布団を干す理由や効果を知っておきましょう。
毎日使っている「布団」は、清潔に見えても汚れが溜まっています。汚れた布団をそのまま放置していると、「カビ」・「臭い」・「ダニ」の原因となります。その詳しい理由と、布団干しの効果を合わせて確認していきましょう。
カビ対策として
季節に関わらず、人は就寝時に大量に汗をかいています。その汗コップ1杯分程度が、布団に吸収されてしまうのです。
そのまま布団を放置すると、吸収した汗が原因で湿気をたくさん含んでしまい、カビが生える原因となります。
布団を干して、布団内部の湿気を逃すことで、「カビ」が生えにくい布団にしましょう。外に干せない方は、布団乾燥機も効果的です。

イヤな臭い防止
寝汗や皮脂汚れがついた布団を放置すると、雑菌が繁殖してイヤな臭いの原因となってしまいます。
布団が吸収した汚れによるイヤな「臭い」は、定期的に布団を干し、湿気を逃すことで、除去することが可能です。
又、布団に取り付けている、シーツやカバーの定期的な取り換え、洗濯表示に沿った布団本体の洗濯も、臭い予防にかなり効果がありますので、できるだけ定期的に行ってください。

ダニ対策
多くのダニは高温多湿を好み、一般に温度15~35℃、相対湿度50~100%の条件で生息しています。
ダニは湿度が下がり、乾燥した環境下だと死滅するので、布団を干すこと自体が効果的な「ダニ対策」となります。
日本の夏は、ダニが好む環境が整いやすく、定期的に布団を干すことが重要です。
又、冬でも人の体温により、布団が保温・保湿され、ダニの好む環境が整いやすくなるので、定期的に布団を乾燥させる必要があります。
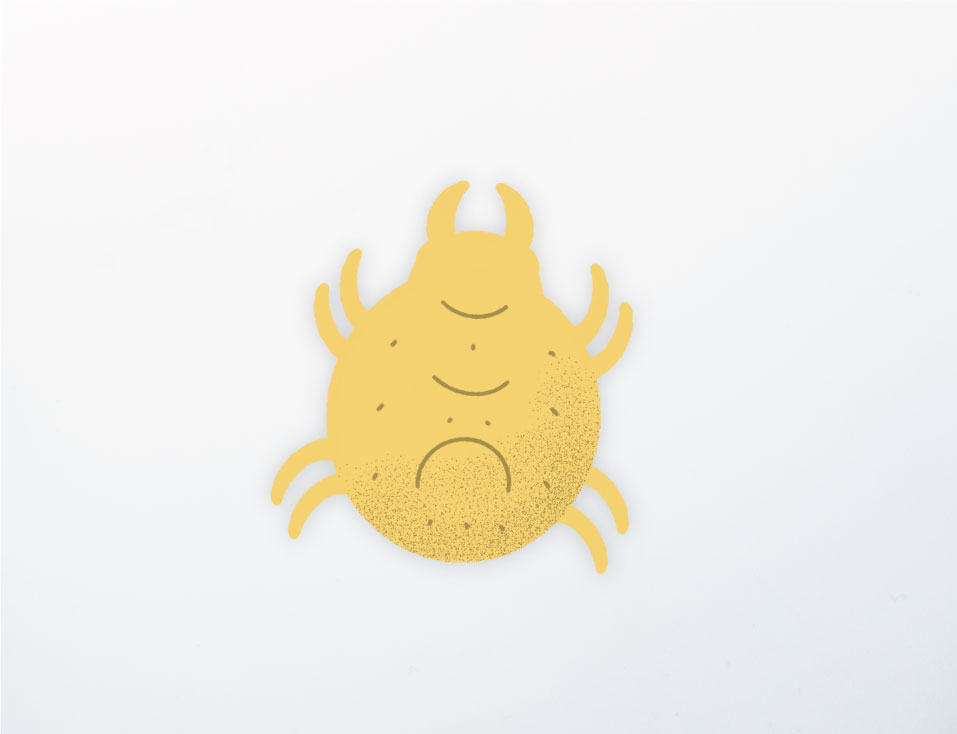
布団の劣化対策
寝汗や皮脂汚れを放置し、湿気が溜まると、布団の繊維が湿気を含み、その分布団が重たくなり、状態が悪くなってしまいます。
布団を干して布団内の湿気を逃すことで、中綿の繊維が軽くなり、ふっくらとした布団に復活させることが可能です。
更に、布団自体も軽くなっているので、就寝中の身体にかかる布団の重さも軽く、快適に眠ることができます。

睡眠の質向上
汗や皮脂などにより湿気を多く含んだ布団を干し、しっかり乾燥させることで「臭い」・「カビ・ダニ」・「布団の劣化」を解消することができます。
これにより、布団の清潔さが保たれ、布団本来のボリュームや肌心地を体感し、毎日の快眠に繋げることができ、「睡眠の質向上」を叶えられます。
睡眠の質が向上し、しっかりと睡眠がとれるようになれば、日々の生活や仕事・学校生活に、しっかり集中でき、健康的な生活を送ることができるでしょう。

3.布団の干し方の基本
布団を正しい方法で干すことで、布団がふっくらと仕上がり、カビやダニ、イヤな臭いの防止にもつながります。更に、間違った干し方をしてしまうと、布団の寿命を縮めてしまいかねません。
ここでは、布団を干す基本的な方法を解説!適切な布団の干し方を知り、寝心地の良い状態の布団を、できるだけ長く保つことが理想的です。
①天気の確認

布団を干す前に、天気予報を確認しましょう。特に注目するのは「前日」の天気。
前日が大雨だった場合、空気中には多くの水分が含まれています。空気中に水分が多いと、布団がその湿気を吸ってしまう可能性が高くなるので、注意が必要です。
前日が雨だった場合は、水溜まりが乾ききっているかを目安に、湿度が下がってから布団を干すと良いでしょう。
もちろん布団干し当日も、低湿度の晴れた日を選ぶことが絶対条件です。布団干し当日も、雨や湿気が多い場合、布団が乾きにくく、そのまま布団を干すと、カビ・ダニ発生の原因となるので、別日に変更することをおすすめします。
②時間帯の確認

布団は湿気を吸いやすいため、早朝や夕方に干すと想像以上に湿ってしまいます。
布団を干すベストな時間帯は、午前中から昼過ぎまでの時間帯。具体的には、10時から15時が最も理想的です。その理由は以下の通りです。
十分に日差しが当たる
午前中から昼過ぎは、太陽の光が強く、布団に十分な熱を与えることができます。これにより、布団が早く乾き、湿気がしっかりと取れるため、ふっくらと仕上がります。
湿度が低い時間帯
午前中は、空気中の湿度が低いため、布団が乾きやすいです。夕方に近づくと、湿度が少しずつ高くなることが多いため、午後から布団を干し始めると、布団が乾きにくい場合があります。
風通しが良い
午前中から昼過ぎにかけては、風の強さが安定していることが多くなります。風通しが良いと、布団が効率的に乾き、湿気がこもりにくくなります。
日が落ちる前に布団を取り込める
早めに布団を干すことで、日が落ちる前に布団を取り込むことができます。日が沈んだ後は気温が下がり、湿度が上がりやすいので、布団を夜まで干しっぱなしにしておくと、せっかく乾燥した布団が台無しに…。布団を取り込まず、夜中も布団を干しっぱなしにするのは必ず避けましょう。
③風通しを確認

布団干しの大きな目的は、布団に含まれる「湿気」を逃すこと!風通しが良い場所で布団を干すことで、湿気を速やかに逃し、乾きがふっくらとして、清潔な状態をキープしやすくなります。
更に、カビ・ダニの発生を抑制し、乾燥時間の短縮も期待できます。
住居内で風通しが良く、布団干しに適した場所は以下の通りです。
ベランダ
家の中でも比較的風通しが良い場所です。特にマンションのベランダは、高階層になると風が強く吹くことが多いため、布団をしっかりと乾燥させることができます。なお、直射日光が当たる位置に干すとより効果的です。(※日差しによる布団の退色・劣化に注意してください。)
庭
庭も風通しが良く、広いスペースがあれば布団を広げやすい場所です。特に風が強い日には、庭で干すと風がしっかり布団に当たり、効率的に乾きます。又、周囲に木や草が少ない場所だと、風がよく通ります。
屋根裏や屋根付きの干し場
天候に影響されないことが一番のメリット。通気口がある場所や、風が吹き抜ける構造になっている場所だと、乾きが早くなります。ただし、湿気が多い日や風が弱い日は、湿気がこもらないよう注意が必要です。
④いざ実践!布団の干し方

カバーやシーツは掛けたままで
カバーやシーツを掛けたまま干せば、布団と一緒に乾燥させることができ、手間がはぶけます。
更に、紫外線による布団本体の退色・劣化を防ぐことができ、布団に直接花粉等がつくのを防ぐことができます。又、黒いカバーやシーツ、布団干し袋(布団全体を覆うことができる専用のカバー)を使うことで、日光を吸収しやすくし、袋内の温度を上げて効率良く乾燥させることができ、湿気とダニ対策の両方が可能です。
ただし、布団の乾燥をより早く確実に行いたい場合や、湿気がこもらないようにしたい場合は、カバーを外して干す方が効果的です。更に、カバーやシーツの紫外線による退色や、汚れの付着は避けられません。状況に応じて、どちらが適しているかを選んで干したり、布団干し袋を有効活用することが大切です。
布団を広げて干す
布団を干すときは、必ず広げて干すようにします。丸めて干すと、部分的に湿気が残り、乾きにくくなります。布団が均等に乾くように心がけましょう。まずは布団表面をしっかり干します。肌が触れて湿気が溜まりやすい表面は、少し長めに干すと良いです。
(冬は布団が結露している場合があるため、状況に合わせて調整が必要です。)
布団を裏返して干す
布団表面がしっかり乾いたら、裏返して布団裏面もしっかり干します。布団の裏側は湿気が残りやすいため、裏返して干すことで布団全体を均一に乾燥させることができます。
布団は厚みがあるので、布団両面を干し、風を当てて効率的に乾燥させることが重要です。日光に当てる際はもちろん、室内で陰干しする際も実践しましょう。
布団を叩かない
布団たたきを使って強く布団を叩くと、ホコリが落ちるんじゃないかと思われがちですが、これは間違いです。実は布団内部の綿がつぶれ、詰め物が詰まり、布団本来の吸湿性や保温力を損なうといった、布団の傷みの原因となってしまいます。布団を叩くことで、ダニやホコリを布団内部に押し込んでしまう恐れもあるので、布団は叩かないでOK。
(※羽毛布団の場合、内部の繊維が細かくちぎれ、羽毛が外に出てしまうといったケースも見られます。)
更に、布団を叩くことでダニの死骸がより細かくなり、布団を室内に収めた際や布団使用時に、細かくなったダニの死骸・フンが室内に浮遊しやすく、床やフローリングなどに付着することが予測できます。ダニアレルギーは、叩いて舞い上がったダニの死骸・フンを体内に吸い込むことで発症しますので、ダニアレルギー対策の面でも、布団は叩かないことが鉄則です。
布団表面のホコリを払う目的の場合は、布団叩きや手で撫でる程度で十分です。洋服用のブラシを使うのも良いでしょう。
⑤室内干しについて

洗濯物の室内干し同様に、室内での布団の干し方も解説します。
室内で布団を干す際は、窓際の日当たりの良い場所や、換気扇の近く等の風通しの良い場所で布団を干しましょう。エアコンや扇風機を使って風を当て、陰干しするとより効率的です。
室内干しなら、天候や花粉等の外的環境に左右されず、自由な時間に布団を干すことができます。
室内干しの場合も、外干し同様に布団を広げて干し、表・裏しっかり乾燥させるのがポイント。
更に、室内での陰干しなら、紫外線による布団の退色・劣化を防ぐことも可能です。
加えて、湿気が多い日や、空気がこもりやすい場所で室内干しをする場合は、「除湿機」を使うと布団が早く乾くのでおすすめです。
ただし、室内に十分なスペースが必要であり、布団をしっかり広げて干せるスタンド等が必要な場合も。背の高いイス等、室内にあるものを使っての工夫が必要です。
最後に、室内干しは乾燥時間が長くかかる場合があるので、布団を取り込む際に湿気が残っていないかしっかり確認しましょう。湿気が残っていると、カビ・ダニの原因になるので注意してください。
4.〈素材別〉布団の干し方
いざ布団干しを実践!と行きたい所ですが、布団干しの時間や頻度の目安はどのくらいなのか?それは、布団の素材によって異なります。
更に、布団の種類でも異なり、掛け布団よりも敷布団の方が汗を多く吸収しており、冬は床との温度差で敷布団と床の接地面が結露で濡れることも…。敷布団は掛け布団よりも頻繁に干して、湿気を除くようにすることが必須です!
代表的な布団の素材ごとに、大まかな季節に応じた目安を紹介しますので、お使いの布団の素材と照らし合わせてみましょう。
| 素材 | 特徴 | 頻度 | 布団の種類 | 目安時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏 | 冬 | ||||
| 綿 | 湿気を吸収 しやすい素材。 |
週に1~3回 | 掛布団 | 2時間 | 3時間 |
| 敷き布団 | 3時間 | 4時間 | |||
| ポリエステル | 乾きやすい 素材。 |
週に1回 | 掛布団 | 1.5時間 | 2~3時間 |
| 敷き布団 | 2時間 | 3時間 | |||
| 羊毛 | 吸湿性・撥水性 に優れた素材。 |
週に1~2回 | 掛布団 | 1時間 | 1~2時間 |
| 敷き布団 | 2時間 | 2~3時間 | |||
| 羽毛 | 湿気を吸収し やすく、乾き やすい素材。 |
週に1~2回 | 掛布団 | 0.5~1時間 |
1~2時間 |
| 敷き布団 | 1~2時間 | 2時間 | |||
5.〈季節別〉布団の干し方
前述の干し方に続き、季節別の布団の干し方についてです。
冬は気温が低く、日差しも弱いため、なかなか湿気が布団から逃すことができません。その日の気温や天気によって調節が必要になります。
又、夏は布団を乾燥させやすいですが、汗もかきやすい季節です。前述の通り、主に敷き布団に汗が吸収されていき、湿気が溜まりやすくなります。
どの季節も快適に眠れるように、布団の干し方や時間を工夫しましょう。
春(3月~5月)
春は気温が上がり、湿気も少ない季節です。天気も比較的安定していることが多く、布団を干すには最適な季節と言えます。
春は風が強い日もありますが、湿度が低く乾燥しやすい季節。風通しの良い場所(ベランダや庭)で干すと、布団が効率よく乾きます。
春の日差しはまだ強すぎないので、午前中から昼過ぎにかけて干すのが理想的。この時間帯は風も穏やかで、布団がふっくらと乾きます。
春は花粉が飛びやすい季節でもあります。花粉症の方は、外で干す前に花粉の飛散情報をチェックし、花粉が多い日は室内干しを検討しましょう。

夏(6月~8月)
夏は非常に暑く、湿気も多い季節です。布団が湿気を吸いやすく、カビやダニが発生しやすいため、布団のケアは特に注意が必要です。
昼間の気温が非常に高く、湿気も多いので、早朝や夕方の涼しい時間帯に干すのも良いです。この時間帯は、湿気が少なく、風も比較的穏やかです。
外に干しても乾きにくい多湿の日は、風通しの良い場所での室内干しをもおすすめ。エアコンや除湿機を使って湿気を逃しましょう。
又、布団乾燥機の使用も効率的です。効率的に布団を乾燥・高温状態にすることができ、カビ・ダニの発生を防ぐことができます。

秋(9月~11月)
秋は気温が適度に下がり、湿度も低く、布団を干すにはとても良い季節です。急激に気温が下がり始めた際は、早めに布団を干し始めましょう。
秋は気温が涼しくなるため、午前中から昼過ぎにかけて干すのがベスト。日差しが柔らかく、湿気が少ないので布団がしっかり乾きます。
日中と朝晩の温度差が大きく、湿気が多い日は、室内干し・乾燥機を使用して乾かすのもおすすめ。

冬(12月~2月)
冬は低い気温と、空気乾燥する季節。湿気も少なく、布団を干しやすい時期です。ただし、気温が低いため、乾燥するまでに時間がかかる場合があります。
日照時間が短いため、昼間のわずかな時間帯に干すのがポイント。午前中から昼過ぎにかけて、天気が良い日は外に干すと効率的に布団が乾きます。
雪の日は、外で干さず、室内乾燥でOK。室内干しの際は、風通しを良くし、暖房や布団乾燥機を効率的に併用しましょう。
寒い日でも湿気がこもりやすいため、除湿機を使用し湿気を逃すことで、布団の乾燥を効率良く促します。

6.布団干しに関するその他のポイント
これまで紹介した、「布団の干し方」から少し視点を変え、布団干しのイメージであり、最大の目的である「天日干し」、「ダニ対策」について、番外編として解説します。
①日光や紫外線にこだわらなくてOK

布団干しと言えば、日光に当てる「天日干し」を思い浮かべる方も多いかと思います。しかし、必ずしも日光や紫外線に当てる天日干しにこだわる必要はありません。確かに、天日干しは理想的な方法の一つですが、状況によっては他の方法でも十分に効果的に布団を乾燥させ、清潔に保つことができます。
そもそも布団干しは、布団の除湿=風通しを良くすることがポイントなので、布団内の湿気を逃がすことが目的の場合は、日光よりも「風通し」が最も重要!扇風機などで風を当てることで、日光に当てることができない室内干しでも除湿が可能です。
又、前述したように、紫外線は布団の退色・劣化の原因になります。羽毛や羊毛だけでなく、綿やポリエステルの布団も、劣化・ごわつきの原因になる可能性があり、布団側生地の退色も進みます。日光にこだわらず、目的に合わせた布団の干し方を選択することが大切です。
②ダニ対策なら天日干しより、「布団乾燥機」にお任せ!

布団のダニ対策を目的として布団干しをするなら、天日干しよりも「布団乾燥機」の使用が大変おすすめです。布団乾燥機なら、ダニが苦手とする高温・低湿度な環境を手軽に作ることができます。
ダニ対策を目的とするならば、重要なのは布団全体を高温にすること。天日干しで日光を当てても、紫外線のパワーだけではダニ対策ができません。その上、布団の表面を高温にして熱くするだけでは、ダニが布団内部に逃げてしまうのです。
ダニは20〜30分間、50℃以上の熱を保つことで死滅すると言われており、布団乾燥機で布団の湿気を逃すことで、湿気が多い環境を好むダニを除去する効果が期待できます。
布団乾燥機を使用する際は、少なくとも30分から1時間程度を目安に乾燥させましょう。温度設定や布団の種類によって異なりますが、しっかりと温めるために、時間をかけることが重要です。更に、布団両面をしっかり乾燥させることもポイント。ダニは布団の裏側や内部に潜んでいることが多いので、布団全体を乾燥させましょう。
③干した布団を収納する場合の注意点
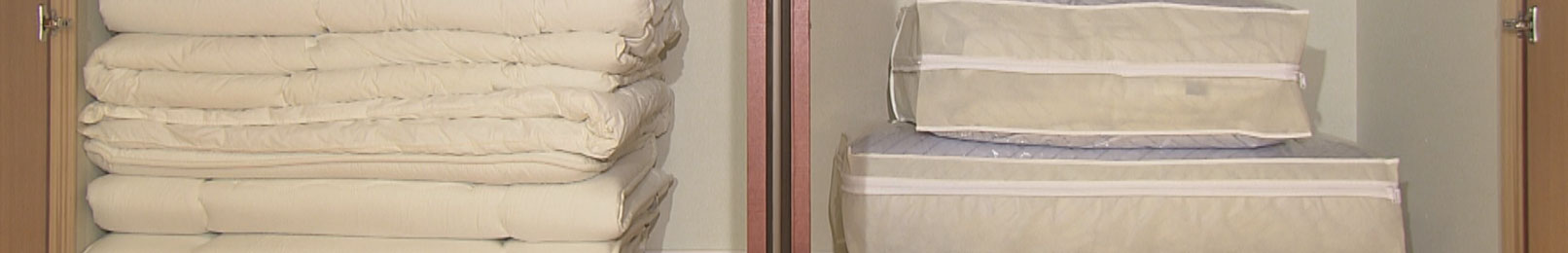
干し終わった布団は取り込んだ後、すぐに収納せず、以下の作業を行いましょう。
布団表面を払う/掃除機をかける
シーツやカバー、布団干し袋を掛けた状態で布団干しを行っていれば、ゴミや汚れ、花粉等の付着を予防できます。しかし、布団の表面に付着したダニの死骸やフン、ホコリをなどを取り除くことはできません。布団を干し終わったら、布団表面をしっかり払う、もしくは掃除機がけを行い、これらをできるだけ取り除きましょう。
掃除機をかけるときは、布団専用の掃除機か、普段の掃除機に専用のヘッドを取り付けて使用します。床掃除用のヘッドのまま使用すると、布団が汚れる可能性があるので注意しましょう。
布団がしっかり冷えてからしまう
布団が温かいまま収納すると、冷えた時に湿気が発生しやすくなります。更に、布団が温かいまま折り畳むと、布団が冷えにくくダニが好むちょうど良い温度環境を作り出す原因になってしまうので、布団が冷えるまで待ってから収納袋に入れて収納しましょう。
7.正しい布団の干し方を意識して、健康的な睡眠ライフを。
正しい布団の干し方はいかがだったでしょうか?ご紹介した干し方を実践することで、布団からイヤな臭いをなくし、カビ・ダニを予防の効果が期待できます。毎日使う布団だからこそ、定期的なケアがとても重要!布団を干すことで、健康的な睡眠ライフを実現する第一歩に繋がります。
布団の干し方は、日光に当てる「天日干し」、エアコンや布団乾燥機、除湿器等を使用しての「室内干し」。どちらもしっかり効果を発揮しますので、住居環境や布団のサイズ等、自分に合った方法で、まずは試してみましょう。
布団の干し方にはポイントがいくつもあり、いざ実践しようと思うと、どうしてもハードルが高く感じられます…。その場合は、まずは布団を干す「目的」に着目!それに応じた布団の干し方から取り組みましょう。
「湿気対策」に目的を絞るなら「布団全体の風通し」にまず取り組み、「ダニ対策」に目的を絞るなら、「布団全体を高温にすること」に限定してチャレンジしてみるのもひとつの方法です。